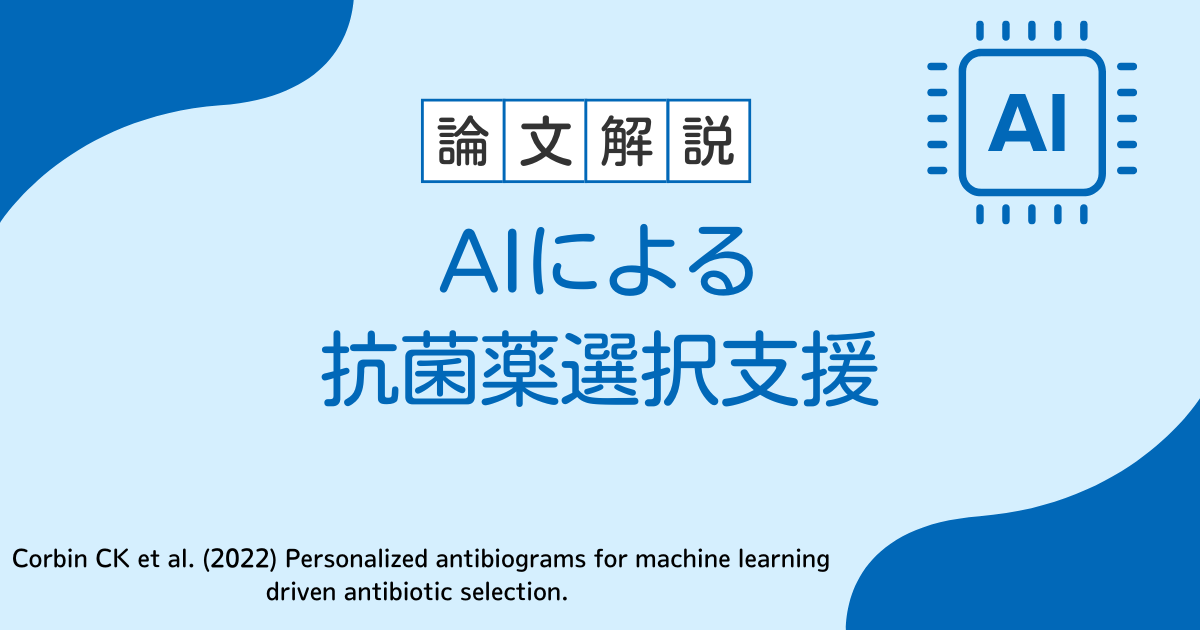導入
抗菌薬耐性は、世界中の医療現場において深刻な問題となっており、WHOは、2050年までに年間1,000万人が薬剤耐性菌による感染症で死亡する可能性があると警鐘を鳴らしています。
実際の臨床現場では、感染症の病原体の特定や感受性試験の結果が判明するまでに数日を要するため、医師はやむを得ず「経験的抗菌薬投与」を行っています。
しかし、このような「広域スペクトラムを優先した」処方は、薬剤耐性の進行や副作用のリスクを高める要因となります。
このような課題を解決するため、スタンフォード大学とボストンの病院グループは、電子カルテのデータを活用し、個々の患者における抗菌薬の感受性を事前に予測する機械学習モデル(Personalized antibiogram)の開発に取り組みました。
研究の要点まとめ
- AI手法
- Gradient Boosted Trees, ランダムフォレスト、L1/L2正則化ロジスティック回帰
- 新バイオマーカー
- N/A(既存の電子カルテ情報に基づく)
- 精度指標
- AUC 0.57〜0.73、感度・特異度は個別モデルごとに報告
- 解釈性
- 特徴量の重要度評価および線形計画法による処方最適化
- 結論
- AIモデルによる抗菌薬選択支援は、医師のカバー率を維持しつつ、広域抗菌薬使用を大幅に削減可能と判明
研究概要
この研究では、機械学習を用いて個々の患者における抗菌薬の感受性を予測する「Personalized antibiogram」を構築し、医師の実際の処方パターンと比較しました。
データは、カリフォルニア州のスタンフォード大学病院およびマサチューセッツ州ボストンにある2つの医療機関(マサチューセッツ総合病院およびブリガム・アンド・ウィメンズ病院)から収集されました。
スタンフォード大学病院では多様な感染症を対象としたデータが用いられた一方、ボストンの2施設では単純性尿路感染症に限定したデータが使用されました。
対象データ
| 症例数 | スタンフォード:8,342件、ボストン:15,806件 |
| 検体種 | 血液、尿、髄液、体腔液など |
| 施設・国 | スタンフォード大学(米)、マサチューセッツ州病院群(米) |
| 研究デザイン | 後ろ向き観察研究(多施設) |
モデル構築
| モデル | GBDT, Random Forest, Lasso/Ridge Logistic Regression |
| データ分割 | 年度別分割(例:Stanfordは2009–2017訓練、2019テスト) |
| パラメータ最適化 | 5-fold CV、Grid Search、Early Stoppingあり |
AIの解析内容
- 特徴量重要度
-
診断コード、過去の感染歴、検査値、抗菌薬の使用歴、バイタルサインなど、合計43,220項目が分析対象となりました。
- 説明可能性(Explainability)
-
バンコマイシンに対する非感受性の予測には、過去の感染歴や抗菌薬の使用歴が特に大きな影響を与えていました。
この予測モデルは、患者の電子カルテ情報に基づき、12種類の抗菌薬(単剤および併用)について、それぞれの感染症に対する「感受性の確率」を推定しました。感受性は、微生物検査の結果により定義されており、検査結果が得られていない場合は、微生物学的なルールに基づいて補完されました。
出力された感受性確率をもとに、線形計画法を用いて、「全体として最も高いカバー率を維持しつつ、広域抗菌薬の使用を抑制する最適な処方の組み合わせ」が算出されました。
スタンフォード大学での検証では、AIモデルにより、医師の処方と同等のカバー率(85.9% vs 84.3%, p=0.11)を維持しながら、バンコマイシンとピペラシリン/タゾバクタムの併用使用を69%削減し、単剤でのカバーを実現しました。
一方、ボストンのデータでは、AIモデルのカバー率が医師の処方を上回る結果(90.4% vs 88.1%, p<0.0001)となりました。
- バンコマイシン(Vancomycin)
- セフェピム(Cefepime)
- ピペラシリン/タゾバクタム(Piperacillin–Tazobactam)
- メロペネム(Meropenem)
- レボフロキサシン(Levofloxacin)
- セフトリアキソン(Ceftriaxone)
- セファゾリン(Cefazolin)
- アンピシリン(Ampicillin)
- メトロニダゾール(Metronidazole)
- アズトレオナム(Aztreonam)
- 単剤のアミノグリコシド(Aminoglycoside)
- 単剤または上記との併用パターン(例:VAN+FEP、VAN+PTZ など)
検査技師の視点での注目ポイント
- 広域抗菌薬の使用を控えることは、腎毒性や耐性菌の増加リスクを低減させるため、患者の安全性向上につながります。
- AIモデルの予測精度は、過去の培養結果や感受性パターンに強く依存しており、検査室における正確かつ迅速な報告がモデル性能に直結します。
- EUCASTやCLSIの基準に基づいた一貫した感受性解釈は、AIの学習精度にも影響を及ぼすため、標準化された検査体制の構築が重要です。
- 感受性データのAI解析結果をICT(Infection Control Team)と共有することで、院内の抗菌薬使用指針の高度化に貢献できます。
- MALDI-TOFなどによる迅速な病原体同定とAI予測モデルを組み合わせることで、初期治療方針の決定時間を短縮できる可能性があります。
- 高齢者、糖尿病、免疫抑制などの患者背景情報は抗菌薬感受性に影響を及ぼすため、今後はこれらの情報を検査システムと連携させることが求められます。
今後の課題とまとめ
本研究は、AIを用いた「個別化抗菌薬感受性予測」が、医師による経験的処方と同等あるいはそれ以上の効果を示すとともに、薬剤耐性対策にも寄与する可能性があることを示しました。
一方で、実際の臨床導入にあたっては、システム統合、リアルタイム処理、モデルの定期的な再学習、感染症の重症度を考慮する必要があるなど、いくつかの課題が残されています。
今後は、培養陰性であっても感染が否定できない症例への対応や、抗菌薬の選択だけでなく「抗菌薬開始の是非」に関する意思決定支援まで視野に入れた活用が期待されます。
検査技師にとっても、微生物データの質を維持しながら、AIと連携した抗菌薬選択支援に貢献することが求められる時代が到来しています。
参考文献
Corbin CK et al. (2022) Personalized antibiograms for machine learning driven antibiotic selection. Communications Medicine 2:38.
DOI: 10.1038/s43856-022-00094-8