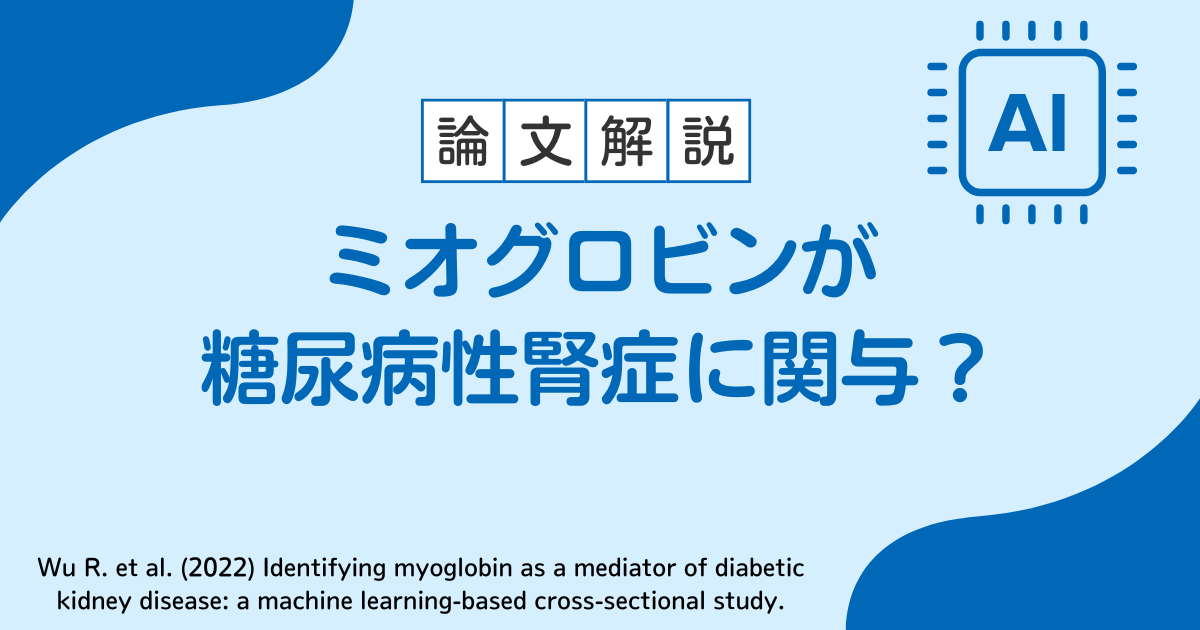導入
糖尿病性腎症(DKD)は、2型糖尿病(T2DM)の患者において頻繁に発生する重篤な合併症であり、約半数の患者が最終的にDKDを発症するとされています。
しかし、メタボリックシンドロームもDKDリスク予測に用いられますが、予測精度も十分とはいえません。
これまでに腎機能指標(eGFRや尿中アルブミンなど)が主要な評価項目とされてきましたが、それらが障害された段階での診断では介入のタイミングが遅れる可能性があります。
こうした課題に対し、近年はAI技術を用いた大規模データ解析によって、新たな予測因子の発掘が期待されています。
本研究では、筋肉由来の酸素運搬タンパク質である血清ミオグロビン(Mb)に着目し、機械学習を活用してそのDKD発症への寄与を評価しました。
研究の要点まとめ
- AI手法
- ランダムフォレスト(RF)
- XGBoost
- SHAP
- RCS
- 因果媒介分析
- 新バイオマーカー
- 血清ミオグロビン(Mb)
- 精度指標
- AUC 0.85
- 感度 0.69-0.72
- 特異度 0.85-0.91
- 解釈性
- SHAP解析によりMbおよびメタボリックシンドローム構成要素(インスリン抵抗性、β細胞機能、脂質代謝)が高重要度と判明
- 結論
- 血清ミオグロビンはDKDリスクの独立した指標であり、メタボリックシンドローム構成因子による腎障害の媒介因子となり得る
研究概要
本研究では、第三湘雅病院における2013年〜2020年の電子カルテデータ51,866件から、糖尿病性腎症に関与する新規因子探索を目的にデータマイニングを行いました。
除外基準により対象患者728例が抽出され、その中でDKD群(286例)と非DKD群(442例)に分類されました。
従来の腎機能指標を含めたモデル(RF-88, XGBoost-88)と、それらを除外したモデル(RF-83, XGBoost-83)が構築されました。
両モデルともAUC 0.80〜0.88と高い識別精度を示しました。
特に、ミオグロビンは腎機能指標を除外しても最重要特徴量として抽出され、メタボリックシンドローム構成要素との関連も強く示されました。
また、Restricted Cubic Spline解析により、血清ミオグロビン濃度80ng/mL以上でDKDリスクが有意に上昇することが確認されました。
さらに因果媒介分析では、インスリン抵抗性や糖代謝異常による腎機能障害の一部がMbを介して発現することが統計的に示唆されました。
対象データ
| 症例数 | 728名(DKD: 286例、非DKD: 442例) |
| 検体種 | 血清・尿検体(電子カルテデータより抽出) |
| 施設・国 | 中国・中央南大学第三湘雅病院 |
| 研究デザイン | 機械学習を用いた後ろ向き横断研究 |
モデル構築
| AIモデル | XGBoost、ランダムフォレスト(RF) |
| データ分割 | 訓練: 60%(2016年3月9日以前)、検証: 40%(以降) |
| パラメータ最適化 | グリッドサーチ+5-fold交差検証 |
AIの解析内容
- 特徴量重要度
-
尿中アルブミン、eGFR、血清クレアチニンなど腎機能マーカーに加え、血清ミオグロビンが上位になりました。
メタボリックシンドローム構成因子(HOMA-IR、IGI、HDL-Cなど)も高順位でした。 - Explainability
-
SHAP解析では、腎機能指標に次いでMb(13位)がDKD分類に寄与。
高ミオグロビン値(80ng/mL超)はDKDリスク上昇に寄与。 - 因果媒介分析
-
メタボリックシンドローム成分がミオグロビンを介して腎機能障害を引き起こす経路が示唆されました。
検査技師の視点での注目ポイント
- 血清ミオグロビンは既存の生化学自動分析装置で測定可能であり、新たな設備投資なしに導入が可能です。
- 糖尿病患者の定期検査にミオグロビン測定を追加することで、DKDの早期リスク層別化が期待できます。
- 早期リスク予測が可能となることで、生活習慣改善や薬物療法の介入開始を前倒しでき、DKD進行の抑制につながる可能性があります。
- SHAPを用いたモデル解釈により、AIに慎重な医療現場でも説明責任が果たしやすく、検査技師が「AIと現場をつなぐ説明役」として活躍する未来が見えてきます。
- DKD分類モデルを構築したうえで、ミオグロビンの関与を統計的に特定した点が本研究の大きな特徴です。
- 電子カルテ(EHR)に蓄積された検査データから機械学習モデルを構築しており、検査部門が保有するビッグデータがそのままAI開発に貢献できる構図を示しています。
今後の課題とまとめ
本研究は横断デザインであり因果推論の限界が残るほか、血清ミオグロビン測定は現在臨床現場で一般的ではありません。
今後は、前向きコホート研究や介入試験による因果関係のさらなる検証が必要とされます。
検査現場での活用に向けて、追加の臨床データが重要になります。
また、代謝異常や筋障害がミオグロビン上昇に関与する可能性もあり、メカニズム解明が待たれます。
本研究は、AIを活用して既存臨床指標の背後に隠れた新規リスク因子を抽出できる可能性を示しました。
参考文献
Wu R. et al. (2022) Identifying myoglobin as a mediator of diabetic kidney disease: a machine learning-based cross-sectional study. Scientific Reports, 12:21411. DOI:10.1038/s41598-022-25299-8